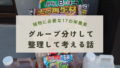今回は、野菜と食の安全性についてのお話から、最終的に「みんなで野菜を作ろう!」という壮大なお話に発展して行きます。どうぞお付き合いいただけますと幸いです。
私自身が、自然食品店の青果担当として勤務した経験から感じた事、農業関係者や流通業者とのお付き合いの中で感じた事、それから自身も含めた消費者としての考えも含めて、なるべく公平な目線で書かせていただきます。
農薬は有害?

私が、自然食品店の八百屋さん担当をしていた当時に販売していた野菜は「無農薬・無化学肥料」という価値をアピールして販売をしておりました。
そういったお店に来るお客様の中には、「農薬」=「有害」というイメージを強く持たれている方が多くいらっしゃいました。
そこで思ったのが、そもそも「農薬」ってどんな物なんだろう?という事です。
辞書によると、
「農薬」・・・農業用の薬剤。
と書いてあります。
では同様に「薬剤」とは
「薬剤」・・・病気や傷を治したり、健康を保持、増進したりするために使うもの。
と、ありますので、そのまんまですが、「農薬」というのは「農業用のお薬」という事になります。
お薬という事は本来「有益」であるべきと思いますが、なぜ真逆な「有害」なイメージとなってしまうのでしょうか?
私も元々は農薬に対しては「化学的な物質が使われている」「体に悪そう」という「有害」なイメージを持っていました。
しかし、よく見ていくと農薬にも色々な種類があります。
そもそも、農薬の目的は「野菜の病気や害虫の被害を減らして生産量を増やす」事です。
問題となるのは、その中に「人体や自然環境に悪影響のある成分」が含まれている場合です。
逆に、天然由来で「人や自然に有害な成分は含まれていない農薬」もあります。
例えば、希釈した「お酢」を吹きかけるという事も、広い意味で言えば「農薬」という事になりますし、アブラムシを食べる「テントウムシ」も「農薬」として扱われる事があります。
ですので、漠然としたイメージで判断するよりも、実際にその薬が「どんな成分」で「どんな効能があるのか」ということまで知る事が大事だという事を理解してからは、徐々にイメージや先入観にとらわれる事が減ってきました。
という事で、「農薬」という物を一括りに考えて、どういう物かわからないままイメージだけで「有害」と決め付けてしまうのは、少々極端な考え方になってしまうのかなと思います。
ですので「農薬の中には無害な物も、有害な物もある。」という風な捉え方が適切かと思います。
農薬の有害なイメージの原因

そこまで「有害」なイメージが強くなってしまった原因としては、農薬によって人間の健康や地球環境に薬害を出した事がある。
という過去の歴史のインパクトが非常に強い事にあると思われます。
または、レイチェルカーソンさんの「沈黙の春」なども影響力が強かったのではないかと思います。
恐らく1970年代ごろは、有害な農薬が市場にたくさん出回っていて世界中で使用されている状況だったのでしょう。
そんな「有害な農薬」を、環境や生物に害があると分かった上で、経済的な利益を優先するために使っていた人々がいれば消費者が怒るのは当然です。
しかし、もしそれでも使わざるを得ない状況に追い込まれていた農家さんもいたとすると、それは相当に辛かっただろうなと想像します。
農業に限らず、資本主義経済でコスパを最優先する社会になってしまうと、必ずこういう不幸な事が起こってしまうという事は残念ながら人間の歴史が証明してしまっています。
有機栽培について感じる事

自然食品店にいらっしゃるお客様は「安心・安全」を強く求めていらっしゃる方が多いです。
私も元々そういう事に興味があったので、自然食品の会社に就職した訳なのですが、特に子供が生まれてからは尚更、食の安全が気になる様になりました。
そういった野菜を購入する消費者側の視点に立てば「有機栽培は安全」で「農薬は有害」ですよ。といった様な「わかりやすい基準」があった方が「安心して買い物が出来るよね」という気持ちもよくわかります。
しかし、そういう基準に安易にすがるのも考え物です。
「有機栽培」という言葉にも色々な捉え方がありまして、「栽培方法」の事を指す場合もあれば、認証機関が定めている「認証制度」の事を指す場合もあります。
後者の「有機栽培」の認定を司っている「日本の認証機関」の基準を見ていくと「食品の安全性を高める為」というよりは「農業が環境に与える負荷を低減する為」という事を主眼としている基準の様に感じます。
環境に優しい農業を行う事で、野菜の安全性の向上につながる事がたくさんあると思いますので、方向性は間違っていないと思います。
そして、様々な方が協力してこの様な制度の実用に漕ぎつけるまでは、大変な苦労があったであろうと想像します。本当に頭が下がる思いです。
しかし、多くの消費者さんがイメージされている様な「食の安全性」を定めている認証とは少し切り口が違うのかなと思ったりもします。
そのイメージのズレのせいなのか「有機栽培は無農薬ですよね?」という様なことも良く聞かれましたが、有機栽培では農薬の使用は認められています。
その代わり「安全と認められた使ってもよい農薬や資材」が定められています。
この「使ってもよい農薬や資材」の決まりは、平たく言うと「化学的に合成された物質」や「遺伝子組み換え」などは駄目ですよ。となっていますので、一定の安全性が保たれる効力があると感じています。
そして「有機栽培」のマークを使用する事が認められるまでの、農家さんのコストや手続きには相当な負担があります。
畑へ使用する資材に関しても、何年も記録を取って準備をしなくてはいけないので、簡単に取れる認証ではありません。
また「有機栽培」と認められた野菜が店頭に並べられるまでの流通・販売の工程にも色々なチェック機能が存在します。
しかし、ここまでやっているのにも関わらず「有機栽培」のマークがあれば絶対安全。という事も残念ながら言いきれ無いとも思っています。
正直「ほんとにこれも有機栽培なの??」と思ってしまう物にも認証マークが付いている事もあります。
特に輸入フルーツなどは、栽培も輸送も品質管理も大変だと思うのですが、平気で認証を受けている物が安定供給されている印象を受けます。
正直、輸入の仕事や現場を見た事は無い状態で書いてますので、もし間違っていたら教えて欲しいです。
私なりに勉強した中では、輸入の過程で「燻蒸処理はしていません」という事が認証の条件の一つなのですが、逆に輸入の現場では「虫が一匹でも発見された場合は、燻蒸処理をしなければいけない」という事が「植物検疫法」で決まっています。
これを外国のスタッフの方々と連携を取りながら、1個1個のコンテナごとに確認し正確に守って行くという事はなかなかにハードルが高い仕事なのではないかなと感じてしまいます。
さらに、青果売場で働いていた実感として「有機栽培」の認定シールを貼るにしても、認定マークの袋に入れるにしても、有機栽培の認証を使用した記録は残しますが、認証機関が全ての商品をチェックする事はありません。
そんな事は現実問題として不可能だと思います。
また、小売店側も毎日大量に届く野菜のダンボールが、お店に届くまでの経過を全て確認出来る訳もありません。
畑にしても流通にしても店舗にしても、各工程で人が作業している以上、間違いが起こる可能性もあります。
そして、もしどこかの過程に悪意ある人が介入すれば、不正な商品が陳列される可能性も無くは無い制度ではあると思います。
何をもって安心・安全と言えるのか?

では、どうすれば安心・安全と言えるのか?
その「基準」を決める事こそが本当に難しい所だと思います。
農薬や肥料の安全基準は、誰がどうやって決めるのか?
どこからどこまでがOKで、どこからはNGとするのか?
考えれば考えるほど、ハッキリ決めるのは難しい問題だと思います。
そうなんですよね。
結果として「これは安全」という基準を設けようとする事には、限界があるなと思っています。
そんなに厳密に重箱の隅をつつく様な事をしていたら、安心して食べられる物なんて限られてしまいます。
そもそも農産物は工業製品ではなく、自然の恵みです。
そこに対して人間の基準で「白か黒か」をハッキリつけようとする事自体に無理がある様にも感じます。
また仮にその「基準」を決めたとしても、皆でそれを管理徹底していく事も大変難しいと思います。
「制度」や「仕組み化」で何とかしようという考え方自体が、もしかしたら旧世代的というかすでに限界を迎えつつあるのかもしれません。
野菜を買うという事

という事で、安心安全を追求するのであれば「自分で食べる分は自分で作る」事が一番確実です。
これは前述の白黒問題をハッキリと解決する一つの有効な方法だと思います。
次点で「親戚や知人が作った物」を分けていただく。という方法も良いと思います。
もし農産物を作って分けてくれる様な親戚や知人がすでにいらっしゃる方は、非常に有難い事だと思いますので、ぜひその方を大事になさってください。
そうやって知人の作ってくれた物で毎日食べる野菜を賄う事が出来れば一番良いのですが、なかなかそうもいかないですよね。
現在の日本では、ほとんどの人が「知らない人が作った野菜」を買って食べている。という社会構造になっています。
選択肢として「知らない人から買う」しかないとするならば、出来るだけ信用出来るお店や農家さんから買いたいですよね。
皆さんはどうやって「信用が出来るか」を判断していますか?
認証マークなどは参考にしつつも、最後は自分の経験や知識や感性で判断して行くしかありません。
そして「知らない人」とは言え、それでも出来るだけ販売者や農家さんの事を知ろうとする姿勢も大事だと思います。
「友人」とまでは行かなくとも「知人から買ってます」ぐらいになれたら良いですよね。
そういったニーズに応えて、消費者へ積極的に顔を見せてくれる農家さん、WEBやSNSで情報を発信してくれる農家さん、産地直送で店舗へ出荷したり宅配をしてくれる様なサービスも増えています。
しかし、私も含め消費者としては「知らない人から買う」という選択肢を取っている時点で、安全性に関してその「お店」や「流通」や「生産者」を「信用するしかない状態」であるという事実を、もっと自覚しなければならないと思います。
買った物に対して、販売側に責任を全て押し付けて何かあった際にクレームをつける様な風潮が蔓延していると感じますが、買う側にもそれを選んだという責任の一端はあると思います。
ですので「どこでどうやって買うのか?」という事を、より積極的に選んで行くべきだと思います。
現在では「知らない人から買う」という事が当たり前になっていますが、昔はもっと自分で野菜を作っている人や親戚や知人に分けている人の割合も多かったはずです。
家族や知人が食べる物であれば、有害と分かっている薬などは使われることは無いでしょう。
ですので、この「自分で野菜を作る」「身近な人に野菜を分ける」という流れがもっと増えたら良いのではないかなと思っています。
野菜を作ることに関心を持つ

という事で、野菜を作る事や食べる事に関心を持つ人がもっと増える事が、安全性の低い野菜が出回らない様にする事にも繋がっていきます。
畑で野菜を作るのはちょっとハードルが高いかな?という人も多いと思いますので、まずは私と同じ様にプランター栽培からやってみても良いのではないかと思います。
社会構造がすぐに変わる事は難しいとは思いますが、今後の日本社会としては農業を含めた一次産業に関わる人がもっと増える事が望ましいと思います。
そして、食の安全性と共に食料自給率も大幅に上げておかないと「何かしらの理由」で輸入に頼れない事情が発生してしまった際には、日本人の食べ物はすぐに無くなってしまいます。
地球温暖化を始めとする自然環境の問題、台風・地震・津波などの自然災害、貿易や戦争などの国際外交問題など「何かしらの理由」になる可能性をはらんでい物は日本にも結構あります。
もちろんそういった事態が起こらないことが一番良いのですが、昨今の自然災害や世界情勢などを見ていると、リスクは低くも無いと思ってしまいます。
みんなで食料を作るという事はそういったリスクを下げる事に繋がります。
ですので、農業や食料を生産することに関心を持つ人が増えるという事は大事だと思います。