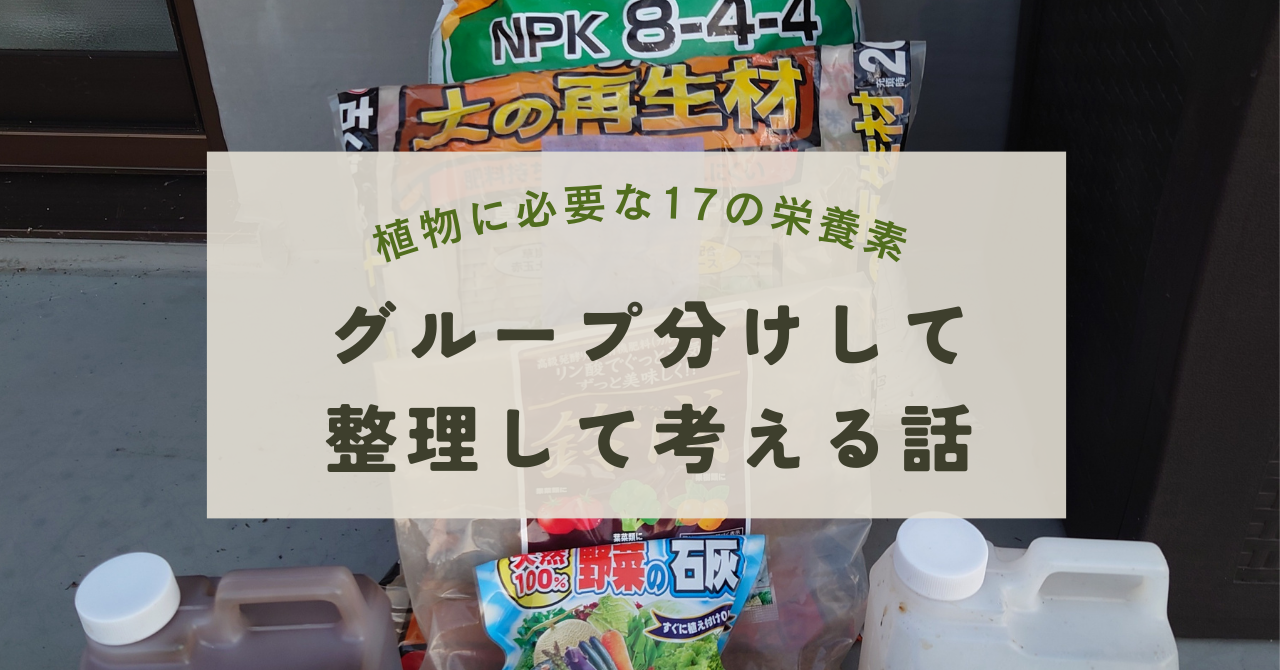プランター栽培をしていると、「土づくり」とか「肥料」とか「栄養素」とか、そういう事が大事だという事はなんとなくわかるものの、どんな種類の肥料をどのぐらいの量を入れたら良いのか?など、結局よくわからずに適当に対応してしまう事ってないですか?
「まあ適当にやって、上手く行く場合もあるし、失敗する事もあるよね」という緩いスタンスでやっていく事は全く問題無いと思います。
むしろそのぐらいの「気楽な気持ちで楽しむ」事も大事だと思います。
ですが、もう少しだけ「拠り所」というか「上手く行くための基準」や「考えの方向性」みたいな物も持っておくと、成功した理由や失敗した理由の検証精度が高くなったり、栽培の経験値もたくさん稼げる様になると思うのです。
そして「土の中で実際にどんなことが起こっているのか?」をイメージする事が出来る様になれば、もっと栽培が成功しやすくなるのではないかと思います。
ただし私などは「栄養素」や「元素記号」などの勉強を始めてみるものの、難解過ぎて眠くなったり、思考が停止してしまう事も多いので、お勉強がなかなか進みません。
ですので、難しい記号などの勉強はほどほどにして「なるべく分かり易く整理して考える」「おおまかな方向性を捉える」というぐらいの感じが丁度良い塩梅かなとも思います。
という事で今回は、植物にとって大切な「栄養素」の事を、なるべく難しくならない様に「おおまかに・分かり易く・整理して」理解を深める事をテーマとして進めて行きたいと思います。
私と同じ様に、趣味のプランター栽培を楽しんでいる方に少しでも参考になれば嬉しいです。
ただし、私の勝手な持論をお伝えしている部分もありますので、もし「化学的に根拠のある理論を学びたい」という方は、別のしっかりしたサイトもご覧いただく事をオススメします・・・。
植物に必要な「17種の栄養素」

まずは基本的な栄養素の話ですが、植物が育つ為に「必要な栄養素」は下記の17種と言われています。
【植物に必要な17の栄養素】
酸素(O),水素(H),炭素(C),窒素(N),リン(P),カリウム(K),カルシウム(Ca),マグネシウム(Mg),硫黄(S),鉄(Fe),マンガン(Mn),ホウ素(B),亜鉛(Zn),モリブデン(Mo),銅(Cu),塩素(Cl),ニッケル(Ni)
この様に、17種類もあるのでひとつひとつを詳しく見て行こうとすると混乱してしまいます。
そこで、なるべく分かり易く整理するために、この17種類を「4つのグループに分けて」それぞれのグループの特徴と、プランター栽培において意識するべき点を併せて確認して行きたいと思います。
【グループ1】自然要素
酸素(O),水素(H),炭素(C)
光・水・空気などの自然環境から得られる要素。
植物の基本的かつ重要な働きである「呼吸」や「光合成」を行う際に必要。
当たり前ですが「呼吸」や「光合成」に支障がある場合は、植物は上手く育ちません。
人間と一緒で植物も「呼吸」をしていますので「空気」が必要です。
葉や茎だけでなく根も呼吸をしていますので、土の中にも空気が通る事が大事です。
そして、植物が活動する為のエネルギーである「炭水化物」を生み出す働きが「光合成」です。
この「炭水化物」が無ければ、植物は基本的な活動をする事も、成長をする事も出来なくなります。
呼吸をするにしても、茎葉を伸ばすにしても、実を甘くするにしても「エネルギー」が必要です。
これらの「呼吸」や「光合成」に必要な要素が「酸素(O),水素(H),炭素(C)」であり「光・水・空気」ですので、何はともあれ大事な要素になります。
【プランター栽培では】
自然環境から得られる栄養素とはいえ、植物が快適に得られる様な環境を整備をしてあげる事が重要です。
「日当り」「水やり」「通気性」「排水性」などを確認し、育てている植物が快適に「光・水・空気」を取り入れられる様に環境を整えましょう。
プランターの置き場所、水やりの仕方、風通しの良い仕立て・剪定、土壌環境作りなど、こだわろうと思うと項目は無限にありますが、基本はこの「光・水・空気」を植物が快適に取り入れられる様にするための環境作りを行うんだという事を指針として持っておくことが大事です。
【グループ2】3大要素
窒素(N),リン(P),カリウム(K)
「3大要素」とも言われ、植物が成長する細胞の元になる栄養素。
必要とされる量が比較的多い為、多くの肥料の主成分となっている。
この3要素は、不足した際はもちろん、多過ぎても問題になる事が多いので「栽培中の野菜に合った量やバランス」で施肥する事が重要。
※肥料成分の表記の例
N-P-K = 8-4-4 など
肥料100g中にチッソ、リン、カリが
8%、4%、4%(8g、4g、4g)含まれているという事を表しています。
※三大要素それぞれのおおまかな役割
窒素(N)→葉・茎を育てる
リン(P)→花・実を育てる
カリ(K)→根を育てる
【プランター栽培では】
「野菜に合ったバランス」というのを細かく考えると難しいので、育てている「野菜の種類」や「成長段階」によって大まかに傾向を把握するという考え方が良いと思います。
それもよくわからない(または面倒くさい)という場合は、どの野菜でも「成長段階」では茎葉の成長を促すためにまずは窒素が必要ですので、窒素が多めの割合になっている肥料(上記の8-4-4など)をメインとして使用していくと無難かと思います。
そのメイン肥料を「追肥するタイミングや量」を、野菜によって調整しながら対応して行くことが出来れば失敗は少なくなります。
注意点として、窒素が多いと葉茎ばかり茂って実付きが悪くなったり、葉や茎が軟弱になり病害虫被害も出やすくなってしまう場合があります。
例えばナス・トマトなど果菜類の実が着き始めた段階では、上記の窒素メインの肥料を控えめにしたり、リン・カリが多めに含まれる液肥なども併用して行くと、収量がアップしたり実の食味が良くなる可能性が上がります。
【グループ3】中量要素
カルシウム(Ca),マグネシウム(Mg),硫黄(S)
「中量要素」として3大要素に次いで重要。おおまかには3大要素の働きをサポートする栄養素。
細胞組織を強くしたり、栄養素の吸収・運搬を助けたり、代謝をサポートする。
3大要素の肥料だけしか使ってない場合は、だんだんと欠乏しやすくなる。
欠乏すると「成長」が弱くなったり、「病気」にかかり易くなる。
「連作障害」は、連作により特定の栄養素が欠乏する事によって起こる場合が多い。
【プランター栽培では】
土の入れ替え・リフレッシュをする際に、元肥と一緒に「苦土石灰」などを混ぜる事で補充できます。
もし土の入れ替えが出来ない場合は、後入れでも補充可能です。
後入れの場合は、石灰などの種類によっては効果がきつく肥料焼けなどの障害を起こす場合もあるので、天然石灰など「即植付可」や「後入れ可」の様な表記のあるマイルドなタイプを選ぶと無難です。
苦土・硫黄やほかの微量要素も配合されている石灰も売っているので、持っておくと便利です。
原肥の場合も追肥の場合も、数か月~半年に1度ぐらいを目安に補充を意識すると良いと思います。
「石灰」がカルシウム、「苦土」がマグネシウム、「硫黄」はそのままです。
石灰と言うと、PH調整の為に使用するイメージも強いですが、このような「中量要素」を補充する意味も同じぐらい重要になります。
例えば「トマトの尻腐れ」などは、カルシウム欠乏の代表的な症状ですので、欠乏させない様にする事である程度防ぐことが出来ます。
【グループ4】微量要素
鉄(Fe),マンガン(Mn),ホウ素(B),亜鉛(Zn),モリブデン(Mo),銅(Cu),塩素(Cl),ニッケル(Ni)
「微量要素」と呼ばれる通り、ほんのちょっとずつあれば良いのですが、全く無くなってしまうのはダメという微妙な栄養素です。
かといってこの微量要素を、一つ一つ測定して調整しようとする人もなかなかいないと思います。
ですので、ここもおおまかな理解で良いと思います。
傾向としては、化学肥料に頼った栽培を続けていると、土の中の細菌が減ってしまい微量要素が欠乏しやすくなります。
有機肥料主体でも、土のリフレッシュをしなければだんだん減って行きます。
足りない物が出てくると、成長不良・病気などが発生しやすくなります。
各種有機物に少しずつ含まれている栄養素ですので、有機物が分解された際に少しずつ発生します。
土壌細菌の種類や数が豊富な程、微量要素もまんべんなく得られる可能性が高くなります。
【プランター栽培では】
新しい作物を植える前に、出来るだけ土のリフレッシュを行い、多様な有機物を混ぜ込む様にします。
私は栽培用のプランターとは別で、堆肥作成用の鉢を作って枯れ葉などを熟成(黒土化)させておき、オリジナルの堆肥を土に混ぜ込む様にしています。
また、ミネラル豊富な海藻由来の肥料など微量要素が含まれる資材も色々販売されています。
それらの有機物に含まれる微量要素が細菌によって徐々に分解され続ける事によって、植物が微量要素を吸収出来る状態が継続しますので、土中に分解できる有機物が常に残っている状態である事が望ましいです。
ただし、未熟すぎる有機物は発酵の際に熱やガスが出てしまう為、プランターの害となる場合がありますので注意して下さい。
自然のバランスを保つ事が大事
植物の種類によって必要とする栄養素も変わってくる為、偏った作物ばかりを育てているとその植物が好む栄養素が欠乏しやすくなります。
その結果「連作障害」の様なトラブルが起こりやすくなります。
土壌や細菌環境も同じ様に偏った種類の細菌が増えてしまうと土壌内の栄養素のバランスも偏ってしまいます。
栄養素の欠乏は良くないですが、一部の栄養素が過剰な状態になってもトラブルの元になります。
ですので「肥料で栄養を足して行く」という考え方より「細菌のエサとして肥料を入れる」という考え方の方が合っている様な気がします。
そして、化学肥料は植物の栄養素としては働きますが、細菌のエサとしては働きません。
化学肥料は無機質なので即効性はピカイチですが、その場凌ぎ的な肥料とも言えます。
継続的に健康に野菜を育てていく為には、有機質肥料をベースとした土づくりを行う事によって、多様な細菌がバランス良く活動する環境を保ち、自然なバランスの栄養素が土壌に継続的に足されて行く事が望ましいと思います。
下記の別記事で土壌改良や肥料について書いてます。参考になれば幸いです。