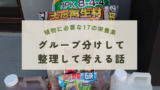なぜ【簡易版】なのか?
今回は「プランターの土の入れ替え・再生作業」という事で実際にやってみるのですが、なぜ【簡易版】としているのか。まずは説明させて下さい。
一般的によく言われている土の再生工程ですと、土の消毒・天日干しなども含めて、数日~数週間もかかってしまうものも多いです。
数日かかるとなると、時間も、手間も、ベランダのスペースもかかってしまいます。
ビニール袋に入れた土を何日も置いたり、作業が何日もかかるとなると、結構大変ではないですか?
一方で、たくさんの野菜を育てる為には、プランターを増やさなければなりません。
プランターが増えると、それだけ土の入れ替えの手間も倍増していく事になります。
それでも、有機質肥料でプランター栽培を続けていくには、土の再生作業は避けて通れません。
しかも、何度も何度も繰り返さなければならない作業です。
ですので、なるべく毎回の負担を軽く、簡単に出来た方が良いですよね。
とはいえ、しっかり再生した土で育てた方が、野菜がイキイキ育ちますし、病害虫のリスクも減りますし、新しい野菜を植える前には、出来る限り毎回プランターをリフレッシュした方が良いでしょう。
必要な事はやって、時短で終わらせる、土の入れ替え【簡易版】というテーマ
美味しい野菜を収穫出来る土にする為に、やるべき事はしっかり行い、それでいて出来る限り簡易な作業内容を目指して行きます。
内容としては、そんなに特別な事はしていませんが、どなたかの参考になれば幸いです。
土の入れ替えの目的
そもそも「土の入れ替え」は「なぜやるのか?」
それは「野菜を健全に育てる為には、土が大事」だからです。
そしてその土を再生・リフレッシュする際に重要なポイントを確認しておきます。
これらが達成出来るのであれば、どんなやり方でも構いません。
- ゴミ、虫を取り除く
- 有機物や肥料の補充
- 酸度の確認と調整
- 団粒構造の再生
こちらの点を意識をしながら、再生の工程を進めて行きたいと思います。
【事前準備】プランターを乾燥させる
土を入れ替えるプランターを決めたら、土の入れ替えの「事前準備」を始めます。
事前にプランターを「乾燥させておく」ことが重要です。
土が湿っていると「ふるい」でゴミを取る際にふるいの目が詰まってしまい、土がなかなか落ちて行かなくなってしまうので、作業がかなり大変になってしまいます。
ですので、作業日の数日前から「水やりは控える」ようにしておきます
天気予報をチェックして「数日雨が降らない日程を選ぶ」か「雨に濡れない様にプランターを管理」しておきましょう。
乾燥した土は風で飛ばされやすいので、出来るだけ「風が少ない日」に行えば、土・砂・ゴミ袋などが扱いやすく、より作業が楽になります。
土のゴミを取る
という事で、数日乾燥させて準備しておいたプランターがこちらになります。
前作のズッキーニの根や、大葉の枯れ葉などゴミが散らかってます。

ここから「古い植物の茎や枝などの残り」と、簡単に手で取れる様な「大きめの根っこ」を取り除いた状態が下記の画像になります。
ここでの主な目的は「ゴミと虫の除去」となります。

ゴミを取り除く
主なゴミとしては「植物の根」「枯れ葉」「枯れ枝」などです。
本来は枝葉や根なども土に残しておけば、いつかは全て分解されて土に帰るのですが、それを待つには少々時間が掛かり過ぎてしまいます。
分解されにくい大き目のゴミは、新しい根が張る際の邪魔になってしまいますので、ふるいに掛かる大きさの物はゴミとして取り除いてしまいます。
ふるいに掛からないような細かい根や枯れ葉のクズなどは、神経質になって取り除く必要はありません。
むしろ多少は繊維質の残渣も残っていた方が、土の微生物環境や栄養のバランスは整いやすくなります。
虫を取り除く
ここで取り除きたい虫は、主にコガネムシや蛾の幼虫です。
ネキリムシ(根切虫)系は、土中に潜んで植物の根を食べます。
ヨトウムシ(夜盗虫)系は、夜の間に地表に出て来て、茎や葉を食べる物もいます。
1匹も出てこない場合も多いですが、土をふるっていく中で1匹見つけた場合は、複数匹出てくる場合がある為、注意深く取り除く様にしましょう。
(※イモムシ系が苦手な方は、下記に画像が貼ってありますので、気を付けて下さい。)
この子らに土の中にいられると、野菜にとっては致命傷となりますので、必ず退場してもらいましょう。
また、コガネムシは成虫になっても葉などを食害しますので、親子共々プランターにはお招きしたくないお客様です。
似ている昆虫でカナブンという子もいますが、カナブンは主に腐葉土(枯れ葉でフカフカの所)に卵を産みます。
ですので、腐葉土ではないプランターでこんな感じの虫を発見したら、だいたい「コガネ確定」と思って良いかなと思います。
それからカナブンの幼虫は枯れ葉、成虫は樹液が主な食糧となりますので、カブトムシなどと一緒に森の中などにいる事の方が多いと思われます。
幼虫も見た目が似ており、見分けるのは難しいのですが、掘り出したときにクルっと体をひねって、すぐにスタコラ逃げ出す子はコガネ、モゾモゾしてゆとりのある感じの子はカナブンの可能性が高いです。
寒くなるとコガネでも動きが遅かったり、蛹になっていたりする場合もあります。
これらの虫は土をふるっておけば発見出来ますので、土ふるいは出来るだけ省略せずに行いたい工程となります。
例外として、腐葉土で堆肥を作っている場合や、数か月以上作物を育てる予定が無いプランターの場合は、土に残った根やゴミを積極的に食べて分解してくれるので、土に残しておいて活動してもらった方が良いですね。
土ふるいをして、ミミズじゃないイモムシが出てきたら必ず退場してもらう。
【プランターでこの顔をみたら110番】

(余談)コンパニオンプランツとしての大葉
ここからは少し余談になります。
先程のプランターですが、まず大葉を引っこ抜こうとして、根本から引っ張ってみると、下記画像の様に根がプランターのほぼ全域に広がっており、土が全体的にガバッと持ち上がってきました。

シソ科である大葉やバジルは、ナス科やウリ科など色々な野菜と相性が良いという事で、コンパニオンプランツとして一緒のプランターで育てる事もあったのですが、今回この根っこを見て少し考えを改めました。
今回は主役のズッキーニが枯れてからしばらくの間、大葉の独壇場だったので、その分余計に根を張ったという事もあるかもしれません。
しかし大葉やバジルは強い植物ですので、プランターの限られた面積の中では、主役の野菜の領土を奪ってしまう可能性が高そうです。
コンパニオンプランツを植える際は、単に栽培の相性だけでなく、根の張る深さやプランター内の勢力のバランスなどもしっかり考えて植えるべきだなと反省をしました。
土ふるい作業
プランターのゴミを取る準備が出来たら、土ふるい作業のセッティングをします。
プランターを全部ひっくり返して、全てリニューアルするというやり方でも良いと思います。
しかし、今回のプランターには鉢底石がバラバラに入っておりまして、石を選り分けるのが面倒なので、このままいっちゃいたいと思います。
鉢底ネットや、ネットに入っているタイプの鉢底石を使っている場合は、石を選り分ける必要が無いのでひっくり返しても良いのかなと思います。
土ふるいの負担を軽くするために、道具の準備と作業前のセッティングが大事です。
私は下記の様に、プランター、シート、ゴミ袋、イスを並べてから作業を開始しています。

ここで「土の入れ替え三種の神器」が活躍するのですが、各グッズの詳しい特徴は別記事でまとめてあります。興味がある方はこちらもご覧ください。
結構大事なポイントとして「イスに座って作業」する事で、足・腰の負担がかなり軽減されます。
またその際に、柄が長いシャベルを使うと、土をすくう作業が格段に楽になるので大変オススメです。
また、ペットボトルはゴミ袋を押さえる重しとして意外と重宝します。

あとはドンドン土を入れて、ふるいを振るだけです。
この時に土が湿っていると、ふるいの目が詰まってしまい、なかなか土が下に落ちて行かない為、地獄の作業となってしまいます。
土が乾燥していてサラサラと落ちていくと非常にスムーズに作業が進みます。

振っていくと、画像の様なゴミが残りますので、ゴミ袋へ捨てます。
網の目はあまり細かい物でなくとも、これぐらいの根やゴミが取れれば十分かと思います。
あとは、プランターの土が無くなるまでこの作業を繰り返すだけです。
ここで取れた鉢底石は再利用するため、ゴミとは別に選り分けておき、後ほど鉢底に戻します。
有機物・肥料の追加、酸度調整
土ふるいが終わったら、土をリフレッシュをする為の肥料や資材を混ぜ込んでしまいます。
そして、この段階で次に作る野菜をイメージして、その野菜に適した肥料の追加や酸度の調整が出来れば、尚良しです。
今回は、この後スナップエンドウの栽培を予定していますので、PHを中性寄りに戻すために苦土石灰を普段より多めに入れました。
ただ、酸度に関しては後でも測れますし、有機石灰は後入れもできますので適当で大丈夫です。
微生物のエサとなり植物の栄養素の元になる有機物をしっかりと補充する事が重要です。
主要な栄養素である窒素、リン、カリ(N-P-K)や、中量・微量の栄養素の元を補充します。
私は先程、酸度調整として苦土石灰を入れましたが、酸度調整よりもむしろ苦土石灰でマグネシウムとカルシウムをしっかり補充する目的の方が重要だと思って入れています。
植物に必要な栄養素に関しては別記事で掘り下げてますのでぜひご覧ください。
どんなものを入れて良いのかわからない。という方は、各メーカーから出ています「土の再生材」的な物を混ぜていただくのが一番簡単です。
各種資材の袋には、それぞれの適量が書いてありますので、おおまかに従っておけば良いと思います。
私は主に、N-P-K主体の有機肥料、微量要素も配合された苦土石灰、それから堆肥用プランターで自作した枯葉堆肥などを混ぜ込んでいます。
これらの資材で微生物環境が良好になっていけば、病原菌が活性化するリスクも抑えられます。
出来れば科学的に成分の分析をして、根拠のある栄養バランスの土を作りたいと思ったりもしますが、あまり頑張ってしまうと、「土のバランス」を取る為に「私生活のバランス」が崩れてしまいそうですので、ある程度ザックリとやっています。
良い意味で適当にオリジナルブレンドを試して楽しむぐらいの方が、趣味として長く楽しく続けられるかもしれません。
とはいえ、正しい知識はあるに越したことはありませんので、私自身も引き続き土や栄養素の勉強は続けて行きたいと思います。


土の状態を良くするためのオススメ資材については、下記ページに詳しく載せてあります。
興味がある方はご覧ください。
土の団粒構造の再生
プランターの土は消耗すると、団粒構造が失われ砂の様になってきたり、ガチガチに間が詰まってきたりして、通気性や保水性などが損なわれて行きます。
ですので、なるべく土のフカフカ感を復活させるためにも土の再生材や枯葉堆肥に入っている繊維質な有機物が大事になります。
それらが混ざる事でフンワリ感が出て、通気性・保水性など土の物理的な性能も回復します。
さらに、出来るだけ多種多様な有機物(前作の残渣、堆肥、肥料、米ぬかなど)が入っている事が理想だと思います。
それらの多様な有機物に対して、それぞれの有機物を好物とする多様な細菌・微生物が集まってきて、活き活きと分解・発酵をする事により、土の団粒化も促進されます。
細菌や微生物が活動する際に出す、粘液や排泄物なども土の団粒構造を回復してくれます。
これらの細菌活動は、適度な水分と温暖な気温によって促進されますので、土の再生は少し暖かい時期に実施する方が良いと思います。
もはや土というよりも、菌が良く働いてくれる「ぬか床」を作るようなイメージで、材料を十分に混ぜ込んだら、プランターに土を戻していきます。
最後に木酢液や微生物資材の希釈液をかけてまた混ぜます。
画像は霧吹きになってますが、潅水の方が楽ですね。
木酢液は殺菌作用のイメージが強いですが、微生物のエサとしても優秀な有機物資材です。

殺菌・消毒について
土をプランターに戻し終わりました。
この段階で、ジャボジャボと熱湯をかけて殺菌消毒したり、ゴミ袋に入れて日光で蒸す事も可能なのですが、私はやってません。
それは面倒くさいから…という訳ではなく、そもそも消毒をする必要があるのかな?と思っております。
病原菌はいたるところにいますので、それらを一時的に殺す事が出来たとしても意味があるのかなと。
ヘタな殺菌・消毒よりも「病原菌が活性化しない環境」を準備する事の方が大事
その為に、しっかり発酵させた有機物や堆肥を混ぜて土壌の栄養バランスや、微生物環境のバランスを良くする方が、結果として病気の予防につながるのではないかと考えているからです。
そして消毒をしなかった事が原因で、次のプランターが病気になった事も無い為、いつからか熱湯消毒はやめてしまいました。
これは我が家のプランターの場合ですので、消毒しないと心配な方や、前作であきらかに病気が進行して病原菌勢力が活発だったと思う場合は、殺菌消毒して病原菌勢力を抑えておいた方が良いのかもしれません。
作業完了(あとは微生物にお任せ)

翌朝です。
スッキリと土がリフレッシュされました。
いろいろと省略はしましたが、これで十分に気持ち良い土になったと思います。
そして、出来上がった「土の臭い」も気にしてみてください。
森の中の黒土の様な匂い(カブトムシがいそうな感じ)や
発酵食品(味噌・醤油・麹)の様な匂いがすると良い土になっています。
これらの匂いがするという事は、有機成分がまだしっかり残っており、微生物の活動が良い状態で続いている証拠なのかなと思います。
このプランターはこのまますぐに植え付けても大丈夫なのですが、「すぐに植付は出来ません」という注意書きのある資材もあったりしますので、そういう物を混ぜている場合は指示に従いましょう。
もし時間が許すのであれば入れ替え完了後は、この状態でもうしばらく寝かせておいた方が無難です。
堆肥の発酵が未熟な場合は、時間を置いた方が良いです。
次回のスナップエンドウまで、まだ余裕があるので、このまま2週間程は置いておこうかなと思います。
その間は、適度に水分を入れつつ、細菌の活動に適した状態をキープしてあげましょう。
有用菌は空気を好むものが多いですので、なるべく耕して換気をしつつ、風通しと日当りが良い暖かい所に置いておきます。
その間にも土の中の細菌たちが元気に活動して、団粒構造も復活しバランスの取れた栄養素を含んだ、さらに良い土になってくれると思います。